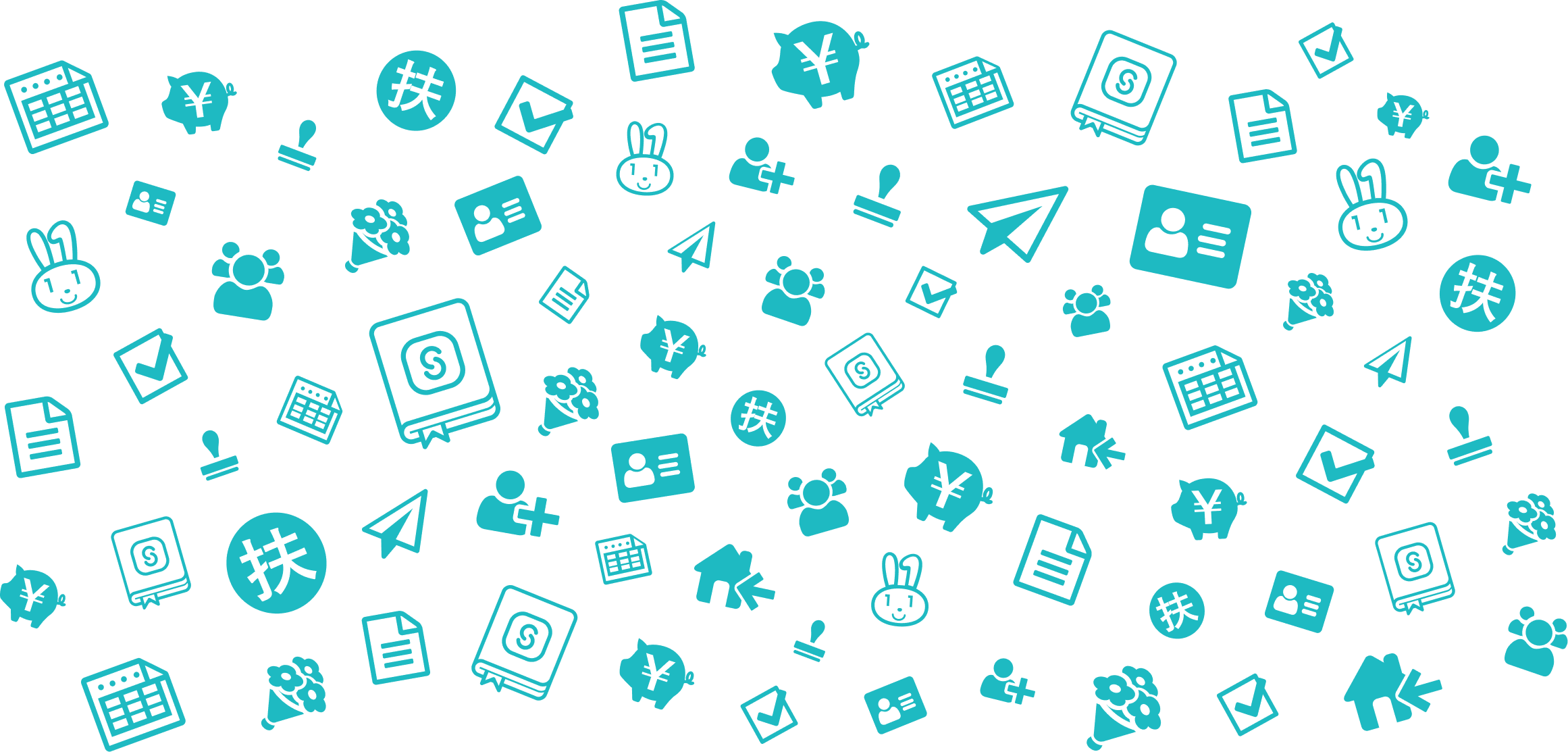住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
SmartHRの年末調整機能で、住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件を説明します。
当ページでは、作成対象外となった従業員が「アンケートでどのように回答して対象外となるのか」の具体例も紹介しています。
目次
- 対象外となる条件
- 年末調整で住宅ローン控除を申告できない方
- SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成できない方
- ※1 連帯債務の借り入れを複数している方
- ※2 家屋の購入と増改築のどちらの控除も受ける方(イ欄とチ欄の両方に日付がある方)
- ※3 住宅ローン控除申告書の各項目が2段に分かれて金額が記載されている、または、書類が2枚に分かれている方(住宅借入金等特別控除が2件以上ある方)
- ※4 重複適用(の特例)を受ける方
- ※5 平成31年以降に居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除証明書の「家屋に関する連帯債務割合(ニ欄)」と「土地に関する連帯債務割合(ト欄)」に記載されている割合が異なる方
- ※6 平成30年までに居住を開始した場合の様式の書類をお持ちで、住宅ローン控除申告書の「⑭欄」に取り消し線がある方
- ※7[特定増改築等の費用の額]に記載がある方
- アンケートの回答により申告書作成対象外となる3つのパターン
- 対象外となった場合の対応方法
対象外となる条件
このヘルプページを読むにはログインが必要です。
SmartHRのアカウントでログインしてください。ログイン
SmartHRのアカウントでログインしてください。ログイン