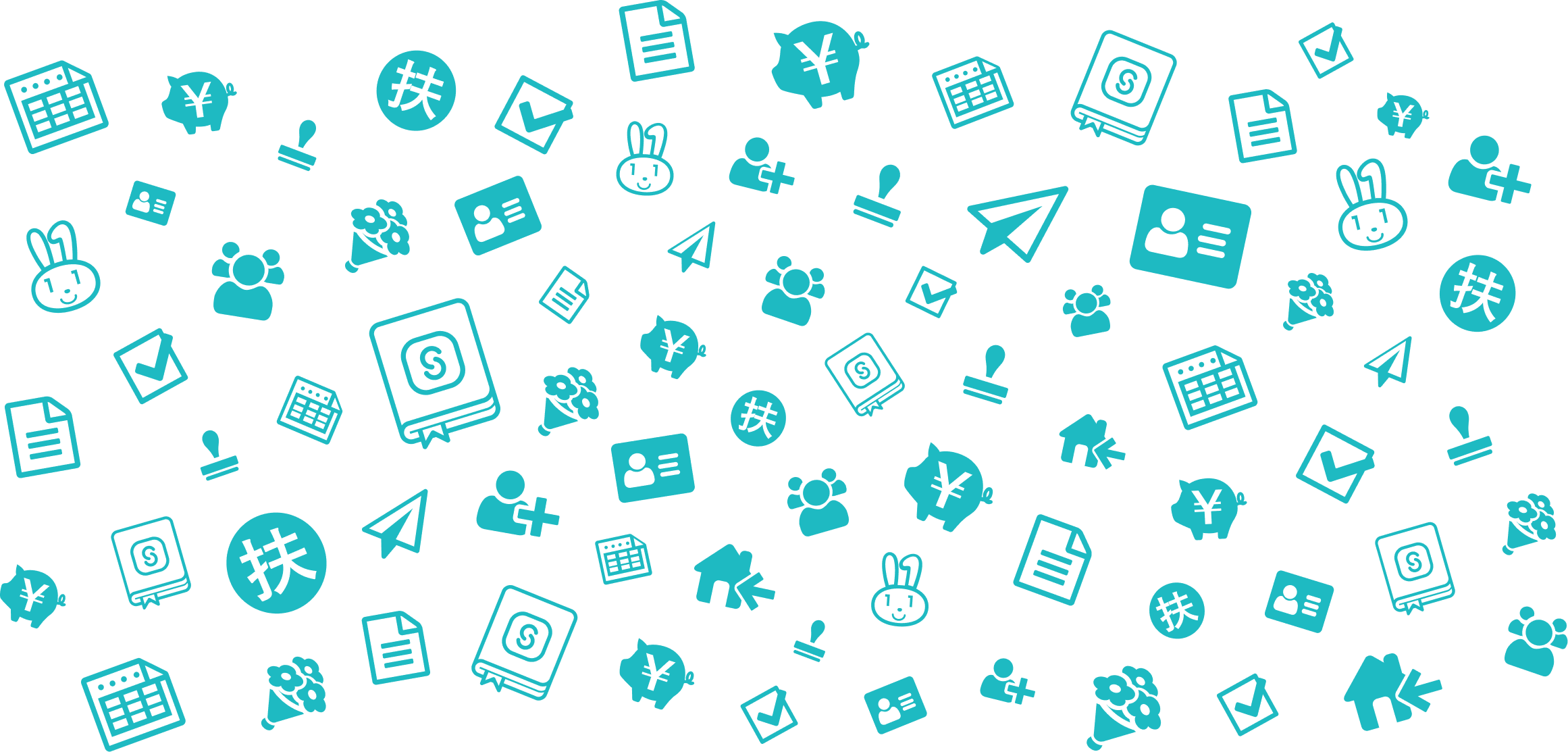税法上の扶養家族とは
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け従業員向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
このページでは、家族情報を追加する際の[税法上の扶養状況]の入力方法について説明します。
税法上の扶養家族とは
納税者(従業員本人)が所得の少ない家族を扶養している場合、給与から差し引かれる所得税や住民税の負担が軽減される制度があります。
SmartHRでは、この制度の対象となる「源泉控除対象配偶者」と配偶者以外の「扶養親族」をまとめて「税法上の扶養家族」と呼びます。
「扶養する」「扶養しない」の選び方
[税法上の扶養状況]を入力する際は、以下の基準を参考に選択してください。 「所得」と「給与収入」の違いは、[年間所得見積額(1月〜12月)]の入力方法にて説明します。
「配偶者」の情報を入力するとき
[扶養する(源泉控除対象者)]
以下のすべての要件を満たす場合に選択します。
- 従業員本人の今年の所得が900万円(給与収入で1,095万円)以下
- 配偶者の今年の所得が95万円(給与収入で150万円)以下*1
- 従業員本人と生計を一にしている
- 配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者に該当しない
[扶養しない]
上記の要件を満たさない、または他の家族の扶養となっている場合に選択します。
「配偶者以外の家族」の情報を入力するとき
[扶養する(源泉控除対象者)]
以下のすべての要件を満たす場合に選択します。
- その家族の今年の所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下*2
- 以下のいずれかに該当する家族である
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
- 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
- 市町村長から養護を委託された老人
- 従業員本人と生計を一にしている
- その家族が青色事業専従者や白色事業専従者に該当しない
[扶養しない]
上記の要件を満たさない、または他の家族の扶養となっている場合に選択します。
[年間所得見積額(1月〜12月)]の入力方法
[扶養する(源泉控除対象者)]を選んだ場合は、[年間所得見積額(1月〜12月)]を入力します。 ここでの「所得」とは、収入から必要経費などを差し引いた金額を指します。
給与収入のみの場合
扶養家族の収入が給与のみの場合は、収入から必要経費などを差し引いた金額を入力してください。 例えば、年間収入が123万円で必要経費(給与所得控除額)が65万円の場合は「123万円-65万円=58万円」となり、年間所得見積額に「58万円」を入力します。
給与所得控除額の算出方法は、No.1410 給与所得控除|国税庁別タブで開くを参照してください。
その他の収入がある場合
事業収入や年金収入などの場合は、所得の計算方法が異なります。
以下のいずれかに該当する方は、所得が48万円以下となり、所得要件を満たします。
- 65歳未満かつ公的年金等のみ:年間108万円以下*3
- 年金108万円 - 公的年金等控除額60万円 = 所得48万円
- 65歳以上かつ公的年金等のみ:年間158万円以下*3
- 年金158万円 - 公的年金等控除額110万円 = 所得48万円
- 事業収入が「年間収入 – 必要経費 = 48万円以下」*3
詳しい計算方法は、No.1000 所得税のしくみ|国税庁別タブで開くを参照してください。
管理者・担当者の方へ
SmartHRで管理者や担当者の権限を持っている場合、従業員の配偶者について、以下の選択肢を選ぶこともできます。 年末調整の結果を反映する場合などにご利用ください。
配偶者に関する管理者・担当者向けの選択肢
[配偶者特別控除対象者]
源泉控除対象配偶者には該当しないが、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象である場合に選択します。
[扶養しない(同一生計配偶者)]
上記の条件に該当しないが、「同一生計配偶者」の場合に選択します。
[不明]
配偶者の扶養状況がわからない場合に選択します。